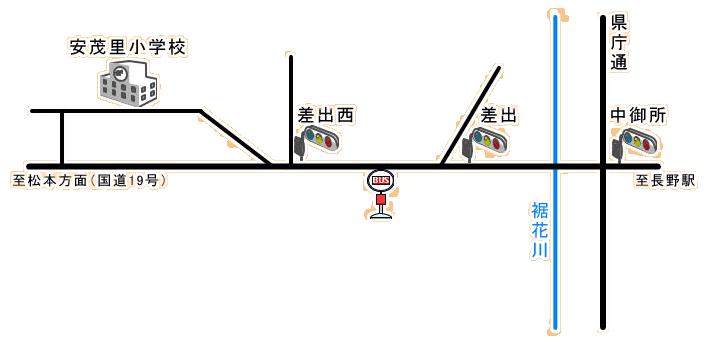| 勝 承夫 作詞 / 平井 康三郎 作曲 | |||||||||
|
校歌再生[MP3/760KB] |
| 明治5年 | 9月太政官布告小学校細則発布 |
| 明治7年 | 正覚院に平柴・小柴見・久保寺・小市の四ヵ村連合「けいぎ学校」設立 |
| 明治10年 | 称名寺に小市支学校設立(後 無常院に移転) |
| 明治14年 | 平柴に矯正学校設立 現在の地に移転 |
| 明治15年 | 安茂里学校と改称 |
| 明治19年 | 小学校令公布 尋常小学安茂里学校と改称 |
| 明治20年 | 安茂里村本堂に校舎を新築 |
| 明治21年 | 尋常小学安茂里学校として発足 |
| 明治22年 | 平柴・小柴見・安茂里の三か村を合併し安茂里尋常小学校と改称 |
| 明治27年 | 日清戦争始まる |
| 明治29年 | 高等科並置 安茂里尋常高等小学校と改称 |
| 明治31年 | 間口十間、奥行き五間の体操場(旧体操場)新設 |
| 明治36年 | 本校校舎増築落成 |
| 明治37年 | 日露戦争始まる 安茂里女子補習学校併設 |
| 明治45年 | 安茂里農工補習学校併設 |
| 大正 3年 | 第一次世界大戦始まる |
| 大正 7年 | 小市分教場全焼 |
| 大正12年 | 関東大震災起こる 小市分教場二階建て校舎落成 |
| 大正13年 | この年より全校遠足運動会・校庭運動会・直江津方面への修学旅行始まる |
| 大正15年 | 講堂兼体操場落成 |
| 昭和 2年 | この年より音楽会始まる |
| 昭和 7年 | 12月 赤心館落成式・赤尾善治郎氏の銅像除幕式 |
| 昭和11年 | 2・26事件起こる 日華事変起こる 学校開墾地開墾作業 |
| 昭和14年 | 第二次世界大戦始まる 防空訓練開始 |
| 昭和15年 | 東校舎全焼 日独伊三国同盟締結 |
| 昭和16年 | 安茂里国民学校となる。10月 赤尾善治郎氏来校し訓話を賜る |
| 昭和17年 | 北校舎増築される |
| 昭和18年 | 学有林が設定される |
| 昭和20年 | ポツダム宣言受諾 太平洋戦争が終わる |
| 昭和21年 | この年より音楽会が毎年実施される |
| 昭和22年 | 教育基本法・学校教育法公布。安茂里村立安茂里小学校発足。安茂里村立安茂里中学校併設。安茂里小学校PTA結成 |
| 昭和26年 | 赤尾善治郎翁石像除幕式 校旗・校歌制定 |
| 昭和29年 | 長野市合併により長野市立安茂里小学校と改称 |
| 昭和30年 | 完全学校給食開始 |
| 昭和31年 | 藤原銀次郎氏来校し講話を賜る |
| 昭和33年 | この年よりパンフレット祭始まる |
| 昭和34年 | プール竣工(立て25m×横12m) |
| 昭和40年 | 松代群発地震発生 南校舎使用中止 |
| 昭和41年 | 新校舎落成 東校舎工事完了 |
| 昭和45年 | 創立80周年記念式典及び新体育館落成記念式典挙行 |
| 昭和46年 | 石炭ストーブから石油ストーブに転換 合唱団結成 |
| 昭和47年 | 小市分校が閉校し松ヶ丘小学校新設される |
| 昭和50年 | 小柴見、平柴(弥勒寺除く)・平柴台の児童山王小学校へ転校 |
| 昭和51年 | 児童会の歌ができる |
| 昭和53年 | 米飯給食開始 |
| 昭和54年 | 南校舎竣工記念式典 |
| 昭和57年 | 新プール竣工式 |
| 昭和63年 | 西校舎竣工記念式典挙行 |
| 平成元年 | 創立100周年記念式典挙行。ビオトープ完成 |
| 平成13年 | 一校一国運動 相手国フランス国際理解教育実施 |
| 平成15年 | パソコン教室改築 情報教育活性化 |
| 平成17年 | よく遊び・よく学ぶ・よくふれ合う杏子っ子の追求 9月 学有林愛護会(安茂里もりクラブ)設置 |
| 平成20年 | 環境教育EMS認定校(EMS・・・学校版環境マネジメントシステム) |
| 平成21年 | 創立120周年記念式典 集合写真・航空写真・読み聞かせ会・ビオトープ整備 |
| 平成24年 | 耐震のため、南校舎補強工事完了 東校舎建て替え開始 |
| 平成25年 | 合唱団NHKコンクール関東甲信越大会にて奨励賞 安茂里小学校PTA 優良PTA文部科学大臣賞表彰 東校舎竣工式 |
| 平成26年 | 体育館と赤心館耐震補強工事 卒業生早川俊久氏グランドピアノ贈呈 |
| 平成27年 | 小校庭 鉄棒設置工事 ヒマラヤ杉伐採 ブランコ設置工事 |
| 平成28年 | ジャングルジム設置工事 オーサー・ビジット |
| 平成29年 | 体育館屋根張替工事 |
| 令和元年 | 創立130週年記念式典 |
 赤心館は昭和7年に建てられた校舎です。赤尾善治郎氏(*)より多額の寄付を受け建築されました。今でも、職員室、図書館などに使われています。
赤心館は昭和7年に建てられた校舎です。赤尾善治郎氏(*)より多額の寄付を受け建築されました。今でも、職員室、図書館などに使われています。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和03年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||